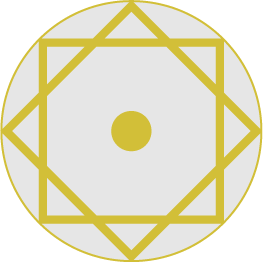先月19・20日と、横浜本部において第4回慈敬学院中級編を開催、北は北海道から南は九州まで、全国会員40名の方が集い、祈りと学びの2日間を共に過ごしました。
新道場になって初めての中級編。しかもコロナ以来、実に4年ぶりということもあって、受講された方もそうですが、私自身も大きな期待と歓びに満ちあふれた機会となりました。
また、今回から中級編の枠組みそのものを変更しました。
それまで「准教師」の資格をお授けするためのプログラムとして構築しておりましたが、そうではなく、准教師はあくまで希望者のみ。資格云々より、多くの会員にこの学びをしていただきたいという意図で、内容や構成を組み直しました。
結果は、本当に充実した2日間というか、身曾岐神社でのⅠを含め計4日間、祈りあり、学びあり、ワークあり、さらに神道、仏教の行(ぎょう)ありで、受講された皆様が真剣、かつ楽しく、終始笑顔で取り組まれていた姿が印象的でした。
特にこの中級編では、日本の信仰の歴史を通して、私たち「かむながらのみち」の使命と役割、その目的・ビジョンについて、あらためて学びます。その大きな視野に立つと、本会の設立に込められた多くの先人たちの想い、何より神仏からの強い願いが胸に迫ります。それを知った受講生の方々は、真に信仰者としての自身の使命に思いを馳せることになります。
また、計4日間、様々な会場の人たちとの交流、身曾岐神社では文字通り寝食を共にすることで、同じ道を歩む者同士としての深い絆を作ることができるのも、中級編の大きな特徴です。今年は9月から第5回を開催、さらに次年度以降も定期的に開催して参りますので、どうか多くの皆様と、この機会を共にしていきたいと存じます。
さて、今月15日に行なわれます「怨親平等大供養」において、私自身が体験したことについては再三、会員の皆様にお伝えしてきておりますが、あらためてここに記します。
今から10年前、ちょうど終戦70年を迎えた年のことです。この怨親平等大供養の10日ほど前のこと。突然背中が痛み始め、夜も眠れなくなりました。その時はちょうど私が主催するセミナーで講師を終日3日間、務めておりましたが、何とかその役目を果たし終え病院にいったところ、帯状疱疹(ヘルペス)だと診断されました。
背中は真っ赤にふくれあがり、まるで火傷でも負ったかのよう。しかも、その翌日から棚経、盂蘭盆会法要、怨親平等大供養と連日大切な行事が続くので、ゆっくり休んでもいられない。何故このような時にと、己に対する腹立たしささえ覚えました。
そんな痛みの中で、私は幾度となく昭和天皇の「終戦の詔勅」、いわゆる玉音放送を聴き、現代語訳を読んでいるうちに、突然胸が熱くなり、あたかも今がその時であるかのような錯覚を覚えました。そして戦いにおいて逝かれた人々の無念の心の痛みや肉体的痛み、あるいは終戦を決断するに至る苦渋の痛み、悲しみの痛み等、その多くの御霊の痛みが私の体を通して現れていることに心が至りました。
私のこの痛みは、もがき苦しみ逝ってしまった多くの御霊に対し、ただ漫然と供養するのではなく、その御霊の想いへと、さらに心を寄せ、想いを深め勤めるよう伝えていただいているのだと悟りました。そして同時に、15日の供養を終えたら、必ずやこの痛みは治まるものと確信したのです。
そして事実、8月15日の「終戦七十年怨親平等大供養」を終えたその夜、痛みはすっかり治まり、発疹も全て引いていました。
私にとってこの10日間は「顕幽一如」の深き真理を垣間見、供養勤める者の心のたたずまいを整え直す貴重な体験となりかいまみました。
本年は、終戦80年ということで、供養厳修の前に「終戦の詔勅」を参座された皆様と共にご拝聴させていただきます。もし、あの時、「この戦争を終わらせなければならない」という昭和天皇を始め先人たちの強い意志と知恵、そして未来への希望がなければ、今の私たちはこの世に生を享(う)けることはなかったはずです。
そのことを決して忘れず、今、日本が平和であることへの感謝と、未来の真の世界平和実現への祈りを共に深めてまいりましょう。
特に、若い世代の方たちにこそ、この機会を共にしていただきたい。そして、平和への想い、未来への願い、これから自分たちがどのような世界を創っていきたいと思っているのか、そういった声を聞かせていただきたいと思っております。
これは、私の知人でありますハワイ在住の本橋タカシさんが2016年、当時の安倍首相が真珠湾攻撃犠牲者に対する慰霊訪問をされた時のことです。本橋さんは、テレビの報道カメラマンとして取材していましたが、かつて兵隊としてこの襲撃を体験されたご老人に対し、中国・韓国のメディアが取材している現場を目にしました。
インタビュアーが、その方に「日本に対してどう思っているか」「安倍首相の演説には謝罪の言葉が一切なかったが、それをどう思うか」などと、しきりに聞いています。おそらく「許せない」などの言葉を引き出したかったのでしょう。
ですが、そのご老人は「謝罪などいらない。そもそもお互いが、それぞれ自分たちの愛する国や家族を守るために戦ったのだから、それに対する謝罪の言葉など必要ない。戦争とは、そういうものだ。だからこそ、戦争は、してはならないんだ」と、毅然(きぜん)と言い放ったそうです。本橋さんは、感動の想いで震える手を抑えつつカメラを回しながら、涙が止まらなかったそうです。
私たち大人は、どうしても偏った目で物事を見がちです。それは何十年という人生を生き抜いてきた中で培ってきた知恵であると同時に、手放すことのできなかった「正しさ」でもあります。
ですが、先のご老人のように、実際に体験してきた人たちの想いが込められた言葉。また若い世代の人たちによる、何の先入観もない中で発せられる言葉には、真にこれからの未来を切り拓(ひら)く力があります。是非、そのような想い、願いをこそ、この終戦80年という年に結集していきたいと存じます。
古代ローマの歴史家クリティウス・ルフスの格言「歴史は繰り返す」。いつの時代も人間の本質は変わりないため、過去にあったことは、また後の時代にも繰り返し起きるということです。ですが、「歴史は繰り返す」のは「歴史は人が創る」からだとも言えます。
その時代の人心に影響を及ぼし、生き方を形成していく基盤は、その時の政治と教育と宗教です。いみじくも、先の参議院選において、自民党が歴史的な大敗を喫しました。私が年頭から申し上げておりますように、今年の干支「乙巳(きのとみ)」の乙は大衆、民意を表わします。その民意が、決然と今の政権に対し「ノー」と告げたのです。
ですが、「ノー」と告げたからには、では何をするのか。どのようにこれからの日本、世界を創り出していくのかを、やはり大衆である私たち1人1人が声に出し、行動していかなければなりません。もはや無関心ではいられないのです。
誰も、戦うことを心底から望んでいる人はいません。ただ、自己の利益、正しさ、生き方を守るために、それぞれの理由が生まれ、戦争という手段をいつのまにか選んでしまう。だからこそ、道祖は「人心救済」――心の救済が先決だと説かれたのです。
歴史は繰り返されるのかもしれませんが、人は進化します。すべての出来事には意味があります。すべてを人格完成、霊格向上の機会として捉え、祈り・受容・超作のもとに生きる生き方。人として最も大切なこと。人が幸せに生きる道――すなわち、この「かむながらのみち」を伝え、広めていく以外、真の世界平和を創り出すことはないのだと、あらためて私たち会員1人1人が胸に刻み込み、そして、新たな行動へと一歩踏み出す。その出発点として、この8月15日「終戦八十年怨親平等大供養」を共に迎えたいと存じます。
今年も残すところあと半年。あらためて己の生き方を見直し、真行者としての使命を生きる誓いを、神仏、ご先祖様、そして多くの先人の方々のみ前で結び直し、日々の生活行、報恩行、そして菩薩行に精進して参りましょう。