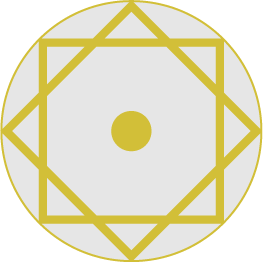石(いわ)ばしる垂水(たるみ)の上(うえ)のさ蕨(わらび)の萌(も)え出(い)づる春(はる)になりにけるかも
志貴皇子(しきのみこ)
『万葉集』巻八の冒頭を飾る春の名歌です。
石の上をはげしく流れる滝のほとりに、さわらびも芽を出す季節になった。冬は去った。さあ、野に出よう――
かむながらのみち本部においては、2月2日に星供護摩法要、ならびに節分立春祭が執り行なわれました。暦の上では春となり、本格的な年明けを迎えたとはいえ、いまだ寒い日は続きます。ですが、もう世の中は新たな動きが様々に始まっています。人生で良い運びを得るためには、天地自然の運行に沿う生き方をすること。この2月は積極的に外に出て、新たな気を頂戴すべく、ご縁ある神社仏閣において、年明けの誓いを神仏前においてされることが肝要です。
私どもの法脈の祖であります真言宗醍醐派総本山醍醐寺では、毎年2月23日に「五大力尊仁王会」が営まれます。そもそもこの仁王法は、810年、時の嵯峨天皇が朝廷内で起こった内紛により未曾有の国難に陥っている状況を救うべく、唐より帰国した弘法大師空海に鎮静の祈りをご依頼されたことに由来します。空海はこれを受け、『仁王護国般若波羅蜜多経法(にんのうごこくはんにゃはらみたきょうぼう)』を厳修、不眠不休で祈り込み、内紛を収め、世は平安を取り戻したと史書にあります。
今年、開創1150年を迎える醍醐寺では、その開創以来、2月15日から7日間にわたる前行を経て、2月23日には仁王会の大法要が厳修され、国家の安全と、人々の「七難即滅(しちなんそくめつ)」「七福即生(しちふくそくしょう)」が祈られます。
その法要は「五大力さん」として、古くから民衆に親しまれており、当日は全国から十数万人の人々が参詣に訪れ、柴燈護摩(さいとうごま)の厳修や、紅白の大鏡餅を抱え上げ、その時間を競う奉納持ち上げ大会など、様々な催しがなされます。
会員の皆さまにおかれましては、既に前行参座等についてのご案内が各会場を通してなされていることと思いますが、是非お出かけいただき、ご自身の運気隆昌と共に、この国、世界の平安に向けた祈りを捧げていただくことを強くお勧め致します。
そして、この2月は初午(はつうま)の月でもあることから、仁王会に参座された方の多くは、その足で伏見稲荷大社へと出向き、ご祈祷されていると伺っております。
初午とは、皆様ご周知のように2月最初の午の日のこと。もともとは和銅4年(711年)2月の午の日に、伏見稲荷大社に神様がご降臨されたことが始まりとされています。稲荷神とは五穀豊穣の神であり、それから発展して諸産業の守護神として広く信仰されるようになりまし
た。
今では午の日に限らず、2月を稲荷神とご縁深い月として、全国各地に3万あるとされる稲荷神社の総本山である伏見稲荷大社は、常にも増した賑わいを見せております。特に事業を経営されていらっしゃる方は、その繁栄発展はもろちん、そこで得た稔りを世の中へとお返しする誓いをされてこられるとよろしいかと思います。
さて、同じく2月の11日は「建国記念の日」となっておりますが、果たしてこの由来について皆様はどれだけ知っておられるでしょうか。
もともとは「紀元節(きげんせつ)」といって、初代神武天皇が我が国を平定され、奈良・橿原宮(かしはらのみや)で御即位された日を、現行暦にあわせて算定したのが2月11日です。明治維新の際、「諸事(しょじ)、神武創業(じんむそうぎょう)の始(はじ)めに原(もと)づく」ことを国の基本方針とした新政府が、神武天皇御即位を我が国の紀元と定め、明治6年に祝日として制定されたことが始まりです。
戦後、アメリカの占領政策によって、この「紀元節」は廃止されました。ですが、やはり国の始まりを祝う伝統をなくすことは、我が国の存在そのものの意味・意義を失うことであるとして、昭和41年、「建国をしのび、国を愛する心を養う日」として建国記念の日が法制化されました。
ただ、このような経緯もあり、現行の建国記念の日と、この国の始まりである神武天皇の御即位を重ねて祝う向きは、今の人々の中にはあまり見受けられません。全国各地の神社をはじめ、私どもとご法縁深き身曾岐神社においても、この日、紀元祭が執り行なわれ、神武創業の礎のもとに建てられた我が国への感謝の祈りが捧げられます。会員の皆さまにおかれましては、この紀元を祝う日に、我が国の基に思いを馳せ、祈りを共にしていただけたらと思います。
このような節目節目における「祭り事」は、私たちの命を支える根幹であり、その意味・意義をしっかりとわきまえながら、礼節の道を踏む――感謝報恩の心を形に示すべく、足を運び、祈りをささげる。そのような人として当たり前の生き方を、是非ご家庭で、地域で、会員の皆さまは率先して範を示していただきたい。
例えば、その年に収穫された新米を神前に奉り、五穀豊穣に感謝の祈りを捧げる新嘗祭が、毎年11月23日の「勤労感謝の日」とされ、その本義が全く顧みられなくなってしまったのも、すべてこの「礼節の道を踏む」という意識、習慣が失われてしまったからです。
見えない世界があって、初めて私たちの生きる見える世界がある――顕幽一如(けんゆういちにょ)ということを、私は常に皆さまにお伝えしておりますが、それを実際の行動で表わし、示すことも、世の善導となる大切な私ども信仰者の使命です。
このような年中行事の意味・意義、また私どもかむながらのみち会員が実践すべき行動と、その基本精神については慈敬学院、特に初級、中級といった段階で皆さまに学んでいただく機会を設けております。
喜ばしいことに、本年第4回の中級編の募集を開始したところ、瞬く間に多数の申し込みがあり、急遽、第5回を年内に開催させていただく運びとなりました。会員諸子の、自身の祈りと学びを高めたい、深めたい、極めたいという思いが切々と伝わり、あらためて私自身も身の引き締まる思いで一杯です。
このかむながらのみちは、日本の伝統精神を踏まえ、それを今の世にふさわしい形に整え、神仏と共にある暮らし、生き方をお伝えするみ教えです。
年頭から再三、申し上げております通り、今年は「行動の年」です。会員の皆さま、お一人お一人の熱意と、その行ないが、世に変革をもたらす、「修験実証」を常に各々の胸の真ん中に据えて生きましょう。
私たちの祈りと行動が、世の目覚め、覚醒となります。この国、世界の平安と歓びをもたらします。どうか、そのくらいの強い確信と覚悟をもって、日々の生活行にまい進していただきたく存じます。
雪解けの水は、その始まりは小さな一滴でも、それが集まり、いつしか大河となって海に注ぎます。本格的な春の訪れは、もうすぐそこまでやってきています。
季節の移り変わりと共に、明るく、温かく、そして大らかな心をもって、お互い様に精進して参りましょう。
合掌禮拝