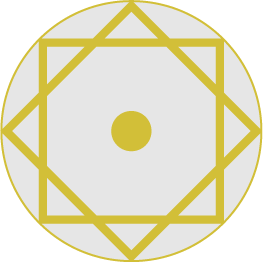先月は梅雨明けを待たずに、日本列島全域で酷暑に見舞われる日々が続きました。四期の運行の乱れもさることながら、急激な気候の変化に体がついていけず、体調を崩された方も多いのではないかと思います。
道祖解脱金剛尊者は、「解脱は病(やま)い直しの道に非(あら)ず、心直しの道なり」と喝破(かっぱ)されておりましたが、同時に、体調を常にベストな状態に整え、心身共に健康なあり方を保つことも信仰者にとって大切な務め。健全な身体に健全な魂が宿ると言いますが、逆もまた然り。健全な身体を維持できないということは、必ずやそこに魔が入る隙(すき)があるということです。
昔はよく、風邪をひいたというと、ご教主から「お勉強」を頂戴した経験のある方は、私も含め決して少なくないはずです。
もちろん「祈れば風邪など治る」などと極端なことを言うつもりはありませんが、自身の体をいたわり、不摂生をしない、規則正しい生活を心がけることも、信仰者の大切な「使命」であると、あらためて胸に刻み込み、厳しい時節をお互い様に乗り超えて参りましょう。
さて、毎年この7・8月は「回向月(えこうづき)」として、お盆をはじめとした祈りの機会を通して見えない世界とのつながりを、常にもまして意識することをお伝えしております。しかも本年は、戦後80年という節目の年にあたり、各地で様々なご法要が営まれ、また報道などでも先の大戦を思い起こさせるものが数多く目にとまります。
私どもも毎年8月15日は「怨親平等大供養」として、成就院において太古以来敵味方にまつわるすべての御霊の鎮魂成仏・霊格向上を祈らせていただいておりますが、今年はより多くの方にご参座いただきたいと思います。
「平和」ということが、より切実な課題となっている今の世界情勢。敵味方の想念・怨念は、核兵器の惨劇を繰り返すことも辞さないところまできてしまっています。節目というのは、同時に変化の機会でもあります。この悪しき流れを断ち切り、人類が覚醒・昇華していくためにも、まずは私たちから祈りの結集です。
これも毎年繰り返しお伝えしておりますが、特に若い世代の人たちをお連れいただきたい。歴史の記憶は時と共に風化していきます。それはやむを得ないことですが、なくしてはならないのは、記憶・記録ではなく、その歴史から学んだ智慧です。
祈りの場を継承していくというのは、その智慧を後代に伝えるということでもあるのです。
――先月、私は長野県伊那市在住の会員・三澤様のお宅に出向き、そのご親族の関係にあたる方の戦没碑のご供養を執行して参りました。
実は以前、三澤家のお墓にまつわるご神示を受け、ご自宅の近くにある墓地へと出向かせていただいたことがあります。その折、お墓自体は特に気になることはなかったのですが、その近辺にあった戦没碑がどうしても気になり、そこで参集された皆様と共にご供養をさせていただきました。
読経が始まると、それまで曇っていた空から太陽の光が差しはじめ、その戦没碑が明るく照らされました。すると、はっきりと2人の人影が碑の表面を通り過ぎていったのです。「どなたか後ろを通っていったのだろう」と、ご供養の間は特に気にすることもありませんでしたが、終わってふと後ろを振り返ると、そこは小高い崖になっており、人が通り過ぎる訳もありません。御霊が感応されたことは明らかでした。
そこで三澤様、そして甲信会場主の藤澤様とも話をして、その碑の祓いとご供養をさせていただくことにしました。当初は、その碑は市の石造文化財であることから、地元の方でお祈りをしていただけばよいと考えていましたが、様々な経緯があり、こちらでさせていただくことになりました。
そのため、その碑に記載されていた文面を調べていったところ、実はその戦没碑に祀られていた三澤家のご先祖の方が日露戦争の戦没者であることが分かったのです。
日露戦争が開戦して間もない明治39年6月15日、陸軍の将兵を載せた輸送船が玄界灘を航行中、ロシアの巡洋艦に襲われ撃沈、1300名にも及ぶ犠牲者を出しました。しかも、何の装備もない輸送船を攻撃したということで、世界中からロシアへ非難の目が向けられ、日本国内でも戦意高揚のため「常陸丸事件」と呼称され、当時様々な形でこの惨劇が伝えられました。その碑は、まさにその「常陸丸事件」で亡くなった三澤家の先祖の方の戦没碑だったのです。
私が念頭から再三申し上げておりますように、今年は日露戦争終戦から120年という節目の年にあたります。そのような時に、今回のご縁というのは決して偶然ではない。これは三澤家だけのことではなく敵味方にまつわる大きな祈り、この碑を通じて常陸丸事件の犠牲者1300有余の御霊と、ひいては日露戦争戦没者を招霊しての祓い供養を行なう旨を伝え、甲信会場の皆様に広く参集をよびかけました。
当日はあらためてその碑にお給仕を申し上げ、三澤家の方々をはじめ集まられた会場の皆様と共に厳かなる祓い供養をさせていただきました。すると、それまでしきりに降っていた雨がにわかに止み、さわやかな風がすっと通りはじめました。御霊がお喜びになっていることを誰もが感じた瞬間でした。
そして今回、私が深い感動と共に受け止めたことは、三澤様ご夫妻と共に、そのお子さん2人も懸命にご供養の準備や対応に励んでいた姿でした。
もともと三澤様は、お子様の課題からみ教えにご縁をいただき、当初から本当に熱心に祈りと学びを進めてこられました。
そして今では様々な課題を乗り越え、一家そろって信仰の道を歩まれています。
「信心相続」と口でいうのはやさしいですが、その実現には親が真剣になって祈ること。そして何より信仰に「歓びと確信」を心から持ち、それをこそ子供たちに伝えていくことなのだと、三澤家のこれまでの経緯をつぶさに見てきた者として、胸が熱くなる機会でもありました。
その甲信会場と富山会場の特別合同会合が、先月8日に本部において行なわれましたが、先の東京・横浜・熊本合同会合に続く、すばらしい会合となりました。両会場主からは、会合終了後、次のような感想をいただいております。
「会合当日は、皆さん新道場の緊張感の中ではありましたが『神は細部に宿る』の如く、この日までの行程に神仏がしっかりとお働きお導きいただけていることを全てにおいて感じさせていただきました。神事仏事においても一体感がある勤行が出来ました。体験発表は発表者と共に真に皆が心からの分かち合いが出来ていました。会合成功の為に1人1人が本気で努力した成果でありました」(藤澤眞司・甲信会場主)。「今回お運びいただいたこの特別会合、まさにお祭りでした。どこの瞬間を切り取っても感動としか伝えられません。両会場主で神事、仏事のお役目にお使いいただきました。異常なぐらいの緊張の中、その時が来ましたが、浜床(はまゆか)に上がった途端、魂が躍動している自分がいました。会員1人1人この日に向けた思いが何よりご宝前に向けてのお供えになり、この素晴らしいお運びを授かったのは間違いありません」(野嶋浩幸・富山会場主)
祈りは魂の覚醒をもたらします。しかも、多くの人が心を1つにした祈りは、大きなエネルギーの塊となって、世の中を動かします。これは古来より、人類が継承してきた叡智です。智慧の結晶です。
どうか、これからも多くの方たちをお連れして、この新本部道場で共に「平和」を願う祈りを捧げていただきたい。特にこの節目を迎えた今だからこそ、できる祈りというのがあるのです。
今年も半年を過ぎました。今年のテーマ「飛翔かむながらのみち」に沿って、これまで生きてきたか、あらためて自身を振り返っていただきたい。飛翔とは、文字通り飛ぶことです。羽ばたくことです。考えたり、ためらったりするのではなく、実行です。歩みはじめることです。「何をしよう」ではなく、「何をしているか」です。
最後に、来月の怨親平等大供養を迎えるにあたり、僭越ながら昭和天皇陛下による「終戦の詔書」をここに掲載させていただきます。多くの方が報道などで「堪え難きを耐え、忍び難きを忍び……」という箇所はよく聞かれていることと思いますが、おそらく全文をしっかり読まれている方は少ないのではないかと思います。
本来であれば、原文を掲げさせていただくところですが、紙幅の都合上、また多くの方にその御心をご理解いただきたいと思い、あえて「定訳」とされている現代語訳を掲載させていただきます。尚、8月15日当日は、この「終戦の詔書」について、あらためて当時の音源を拝聴させていただいた上で、ご法要を営む所存です。
終戦の詔書(現代語訳)
わたくしは、世界の情勢とわが国が置かれている現状とを十分考え合わせ、非常の手だてをもってこの事態を収めようと思い、わたくしの忠良な国民に告げる。
わたくしは、わが政府をもってアメリカ、イギリス、中国、ソ連の四か国に対し四国共同宣言、ポツダム宣言を受諾すねるむねを通告させた。
そもそも、わが国民がすこやかに、安らかに生活出来るよう心がけ、世界各国が共に平和に繁栄していくようにはかるのは、歴代天皇が手本として残して来た方針であり、わたくしの念願を去らなかったところでもある。したがって、さきに米英二国に戦いを宣した理由もまた実に、わが国の自存とアジアの安定を心から願ったためであって、いやしくも他国の主権を押しのけたり、その領土を侵略するようなことはもちろん、わたくしの志とは全く異なる。この戦争がはじまってからすでに四年を経過した。その間、陸海将兵は各所で勇戦奮闘し、役人たちもそれぞれの職務にはげみ、また一億国民も各職域に奉公して来た。このようにおのおのが最善を尽くしたにもかかわらず、戦局は必ずしもわが方に有利に展開したとはいえず、世界の情勢もまたわれに不利である。そればかりでなく敵は新たに残虐な爆弾を広島、長崎に投下し、多くの罪なき人々を殺傷し、その惨害はどこまで広がるかはかり知れないものがある。このような状況下にあってもなお戦争を続けるなら、ついにはわが日本民族の滅亡をきたすようなことにもなり、ひいては人類が築きあげた文明をもうちこわすことになるであろう。それでは、わたくしはどうしてわが子どもにひとしい国民大衆を保護し、歴代天皇のみたまにおわび出来ようか。これこそわたくしがポツダム宣言を受諾するようにした理由である。
ポツダム宣言の受諾にあたってわたくしは、わが国とともに終始アジアの解放に協力した友邦諸国に遺憾の意を表明しないわけにはいかない。また、わが国民のうち戦死したり、戦場に殉ずるなど不幸な運命になくなった人々や、その遺族に思いをはせると、まことに悲しみにたえない。かつ戦傷を負い、空襲などの災害をうけて家業をなくした人々の厚生を考えると、わたくしの胸は痛む。思えば、今後わが国が受けるであろう苦難は、筆舌に尽くし難いものであろう。わたくしは国民の心中もよくわかるが、時世の移り変わりはやむを得ないことで、ただただ堪え難いこともあえて堪え、忍び難いことも忍んで、人類永遠の真理である平和の実現をはかろうと思う。
わたくしはいまここに、国体を護持し得たとともに、国民のまことの心に信頼しながら、いつも国民といっしょにいる。もし感情の激するままに、みだりに問題を起こしたり、同胞がおたがいに相手をけなし、おとしいれたりして時局を混乱させ、そのために人間の行うべき大道をあやまって、世界から信義を失うようなことがあってはならない。このような心がけを、全国民があたかも一つの家族のように仲良く分かち合い、長く子孫に伝え、わが国の不滅であることを信じ、国家の再建と繁栄への任務は重く、そこへ到達する道の遠いことを心にきざみ、国民の持てる力のすべてをそのためにそそぎ込もう。そうした心構えをいよいよ正しく、専一にし、志を強固にして誓って世界にたぐいないわが国の美点を発揮して、世界の進歩に遅れないよう努力しなければならない。国民よ、わたくしの意のあるところを十分くみ取って身につけてほしい。
読売新聞社編『昭和史の天皇4 玉音放送まで』(中央公論新社)より